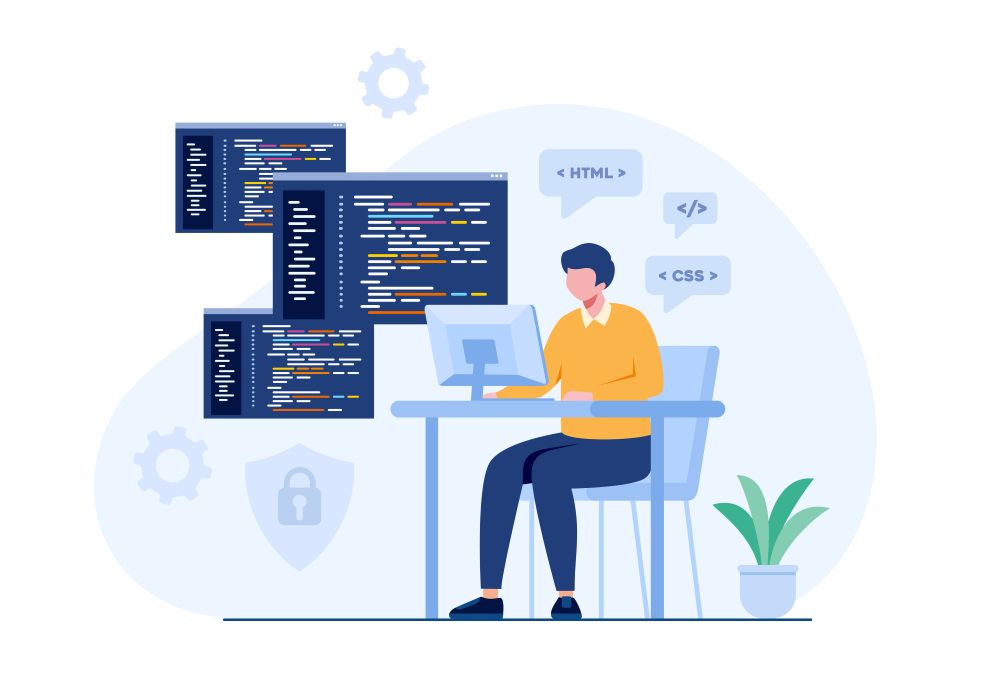関連するソリューション

マネージドサービス(運用・保守)
マルチクラウドは複数のクラウドベンダーサービスを組み合わせて利用する考え方・運用形態です。よく比較されるハイブリッドクラウドとは明確に異なるものですが、その違いは何でしょうか。この記事では、マルチクラウドの概要からハイブリッドクラウドとの違い、マルチクラウドが必要とされる理由などについて解説します。
マルチクラウドとは?
マルチクラウドについて理解するために、クラウドサービスに関する基礎知識やハイブリッドクラウドとの違いについて見ていきましょう。
クラウドサービスに関する基礎知識
マルチクラウドは複数のクラウドベンダーサービスを組み合わせて利用する考え方や運用形態を表します。マルチクラウドについての理解を深めるためには、クラウドサービスの実装モデルとサービスモデルについての基礎知識が欠かせません。クラウドサービスの実装モデルとサービスモデルは、それぞれ次のようなものが挙げられます。
クラウドサービスの実装モデル
- パブリッククラウド:業界や業種を問わずにクラウド環境を提供するオープンな形態
- プライベートクラウド:企業や組織が自社専用のクラウド環境を構築して社内やグループ会社に提供する形態
- ハイブリッドクラウド:上記のパブリック/プライベートの組み合わせや、クラウド/オンプレミスを組み合わせた形態
クラウドサービスのサービスモデル
- IaaS(Infrastructure as a Service):クラウドサービスとして提供されるITインフラのモデル
- PaaS(Platform as a Service):クラウドサービスとして提供されるDBや実行環境のモデル
- SaaS(Software as a Service):クラウドサービスとして提供されるソフトウェアのモデル
サービスモデルは他にも存在しますが、代表的なものとして上記の3つを挙げました。パブリッククラウドとして有名なサービスとしては、Amazon Web Service(AWS)やMicrosoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)などが存在します。加えて、それぞれのサービスモデルとしてはAWSがIaaS、AzureやGCPはPaaS、SaaSモデルのサービスを多く展開しています。
そして、マルチクラウドはこれらのモデルを組み合わせ、自社に最適なクラウド環境の構築を行える考え方・運用形態なのです。
ハイブリッドクラウドとの違い
マルチクラウドは内容が似ていることからハイブリッドクラウドと比較されることが多いでしょう。しかし、両者は明確に異なるものであり、その違いは「システムの統合性」にあるといえます。
マルチクラウドは複数のクラウドサービスを組み合わせ、それぞれを部分的に利用する考え方や運用形態を表します。複数のクラウドサービスは相互に接続せず、それぞれ独立併用しながら運用するものです。
対してハイブリッドクラウドはクラウド環境構築方法の一つであり、サービスを統合して一つのシステムとして運用します。クラウドサービスだけでなくオンプレミス環境との相互接続もあり、クラウドを絡めた相互接続で一つのシステムとして構築するモデルがハイブリッドクラウドです。
マルチクラウドとハイブリッドクラウドは、「クラウドサービスを組み合わせる」という点では同じですが、システムの統合性の点では大きく異なるものであり、明確に違いが存在するのです。
マルチクラウドを利用するメリット・デメリット
マルチクラウドを利用するとどのようなメリットが得られるのでしょうか。併せて、利用する際のデメリットについても見ていきましょう。
マルチクラウドを利用するメリット
マルチクラウドを利用する際のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
- 柔軟なシステムの運用が可能
- 各クラウドサービスの良い点のみが利用できる
- アクセスの分散が可能になり、負荷が軽減する
マルチクラウドを利用する最大のメリットは、柔軟なシステムの運用が可能になる点にあるといえるでしょう。詳細については後ほど詳しく解説しますが、複数タイプのサービスを併用して利用できるため、即応性に長けたシステムの構築が可能です。加えて、複数のクラウドサービスを利用する際には良い点・悪い点が見えてくるものですが、マルチクラウドであれば良い点のみが利用できることもメリットとして挙げられます。
さらに、さまざまなサービスを組み合わせて利用するマルチクラウドであれば、特定の環境に負荷が集中しすぎることも避けられ、システムに対する負荷が軽減します。
マルチクラウドを利用するデメリット
対して、マルチクラウドを利用する上では次に挙げるデメリットにも考慮しなければなりません。
- クラウドサービスの管理が煩雑になる
- コストが高くなる可能性がある
- セキュリティ強度が不統一になる可能性がある
通常、クラウドサービスを利用する際には、ダッシュボードで各種サービスを一元管理できます。しかし、マルチクラウドの場合は複数のクラウドサービスを組み合わせて利用するため、サービスの管理が煩雑になりがちです。
加えて、各クラウドサービスに対するコストが発生することで、単一のサービスを利用する場合と比べてコストが高くなる可能性があります。クラウドサービスの料金体系は少し分かりづらいものであるため、コストの発生条件をしっかりと確認した上で環境を構築しなければなりません。
さらに、各クラウドサービスはそれぞれがセキュリティに対する考え方が異なることから、システム全体のセキュリティ強度が不統一になる可能性もあるのです。
マルチクラウドが必要とされる理由
さまざまなメリット・デメリットが存在するマルチクラウドですが、企業活動における今後のICT環境の構築のために必要とされていることは確かです。マルチクラウドが必要とされる2つの大きな理由を解説します。
システムの柔軟性の確保
マルチクラウドはシステムに柔軟性をもたらし、その柔軟性こそが必要とされているのです。複数のクラウドベンダーのサービスを利用することにより生まれるシステムの柔軟性は、特定ベンダーに依存することによるシステムの固執化を避けることにもつながります。
ICT環境は日々変わり続けており、最適な環境を構築するためにはシステムの柔軟性は必要不可欠です。システムの柔軟性がないためにレガシー化するシステムも多く存在しており、そのようなシステムは更改のたびに多大なコストを要することに。
システムを構築・運用する現在の目的だけでなく、将来的に発生しうる新たな目的を達成するためにもシステムの柔軟性は必要であり、マルチクラウドが必要とされる理由の一つと言えるでしょう。
BCP、DR対策
マルチクラウドはBCP(事業継続計画)やDR(災害復旧)の対策としても有効です。クラウドサービスはそれ自体に冗長性が確保されているものですが、特定のクラウドサービスによる障害でシステムが使えなくなることもあります。
例えば、クラウドサービスの最大手とも言えるAWSでも障害によって利用者のシステムに影響を及ぼしたことがあるのです。マルチクラウドでは複数のクラウドベンダーのサービスを利用するため、特定のクラウドサービスで障害が発生してもシステムへの影響を最小限に抑えて運用できます。
加えて、災害の多い日本ではオンプレミス環境における災害発生時の復旧対策は、システムを構築・運用する上で欠かせない要素となっています。その点においても、マルチクラウドによって複数のクラウドサービスに運用を分散することで、DR対策としても活用可能なのです。
マルチクラウドと併せて注目したいコンテナ技術
マルチクラウドを知る上で併せて注目しておきたい技術としてコンテナ技術が挙げられます。コンテナ技術は仮想化技術の一つであり、OS上に仮想的に複数の独立した領域(コンテナ)を用意し、その中でアプリケーションを動作させる仕組みです。コンテナ技術はOSなどの環境による差異を意識することなく、複製も容易であるためマルチクラウドとの相性が良い技術となっています。もちろん、クラウドベンダーによる違いも意識する必要がなく、システムの柔軟性を最大限に確保できる技術なのです。
マルチクラウドを実現する際には、コンテナ技術についても併せて覚えておくとよいでしょう。
まとめ
マルチクラウドは複数のクラウドベンダーサービス組み合わせて利用する考え方・運用形態です。ハイブリッドクラウドとは違い、一つのシステムとして統合して利用するのではなく、それぞれの環境を独立して運用します。そのため、柔軟なシステム運用が可能になり、各サービスの良い点のみが利用できるメリットなどがあります。
その反面、管理が煩雑になることやコストが高くなる可能性がある点はデメリットです。しかし、今後の企業活動におけるICT環境の構築において、システムの柔軟性やBCP・DR対策は欠かせないものであり、それこそがマルチクラウドが必要とされる理由として挙げられるでしょう。
加えて、マルチクラウドを利用する際には、近年注目を集めているコンテナ技術と併せて検討してみてはいかがでしょうか。
当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。
エバンジェリストによるコラムやセミナー情報、
IDグループからのお知らせなどをメルマガでお届けしています。