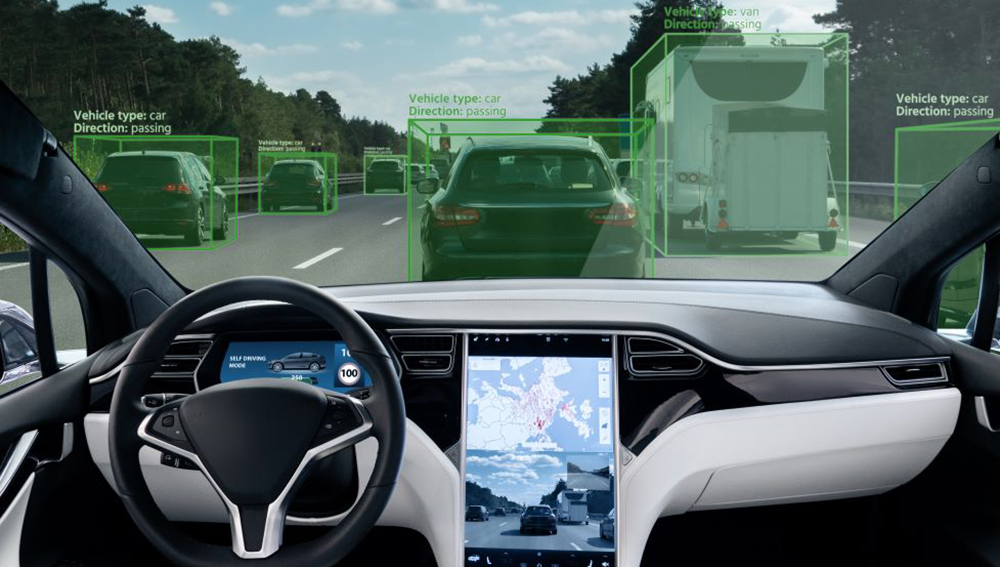株式会社IDデータセンターマネジメント
テクニカルスペシャリスト 水谷 知彦 
IDデータセンターマネジメント所属テクニカルスペシャリスト水谷です。
最近、食品廃棄問題に関連するニュースや記事などをよく見かけます。どの程度食品が廃棄されているのか調べたところ、日本では令和元年の消費者庁のデータで年間570万トンが廃棄されているとのことでした。この量は毎日大型(10トン)トラック約1,560台分に相当するとのことです。よく冷蔵庫の中で野菜や果物を放置したままにして、変色やシワシワになった状態のものを週末まとめて捨てている私には、なかなか考えさせられるデータになりました。
世界に目を向けるとアメリカでは、年間4,000万トン、世界では、年間約13億トンの食糧が廃棄されているとのこと、もうトラック何台分になるか計算したくなくなってくる量になってきます。多くの食品が廃棄されている中、食品が余っている状況とは逆に、食品が不足している状況、飢えや栄養不足で苦しんでいる人たちは、世界に約7.7億人もいると言われています。5歳未満の発育阻害は約1.5億人、日本でも子供の貧困は、7人に1人の割合です。
単純に廃棄する食品をそのまま必要な人に渡せば、食品廃棄問題も食品不足の問題も解決しそうに勘違いしてしまいそうですが、食品の保管、輸送、廃棄する食品と必要な人をつなぐ仕組みの整備などの問題から、食品廃棄と食品不足の問題は簡単には解決してくれない状況です。
では、食品廃棄、食品不足、サステナブル(持続可能)な食品確保のため、世の中でどの様な取り組みが行われているか、ここから少し見ていきたいと思います。
1.廃棄される食品の削減
最近、日本の多くの身近なスーパー、コンビニ、食品店などでも取り組みが行われているこの施策は、私がこちらのコラムで書くまでもなく、コラムを読んでくださっている皆さんの方がよくご存じかもしれません。
ひと昔前まで店頭に並ぶ食品は、大半が形の整った傷のないものばかりでした。多くの消費者もその状態が当たり前と思い購入していましたが、その裏で外見上の問題だけで店頭に並ぶ基準に達しない多くの食品が廃棄されている状況でした。この様に外見上の問題だけで大量に食品が廃棄されている問題に対して、対策として外見に問題があっても販売を行う取り組みが、近年多くの食品販売店で行われています。

最近、店頭で不揃い、訳あり、傷ありなどで表記された食品を見る機会が増えてきていますが、この様な食品が増えてきている理由の多くは、廃棄される食品の削減に起因するものとなります。
個人的に栄養価などに大きな違いがなければ、多少割安で購入できるこのような食品は、もっと多くの販売スペースを取っても良いのではないかと考えます。本来廃棄される食品を販売できることで、生産者の負担も減り、生産量も抑止できると考えますので、最終的に廃棄される食品の削減になると考えます。また、食料不足になると外見上の問題など言っていられなくなりますので、今から外見を気にしない習慣を身に付ける訓練にも良いかと考えます。
2.遺伝子組み換え食品
アフリカの一部地域では、近年干ばつの被害により、深刻な食糧不足が続いています。干ばつにより水が不足し、害虫、病害の影響もあり、農作物の収穫量が減っています。この状況に対して、解決策の一つとして遺伝子組み換えの農作物があります。
遺伝子組み換えの農作物は、通常の農作物と比較して少量の水で生産でき、特定の害虫、病害に強い特性を、遺伝子を組み替えることで付与することが可能になります。アフリカの一部地域では、この遺伝子組み換えの農作物導入が進んでおり、自給自足による食料不足解決に向けて対策が進んでいる状況です。今後、地球温暖化による急激な気候変動が継続的に発生する環境になってしまった場合、急激な環境変化に耐えられる、遺伝子組み換えの農作物による食糧確保の重要性が高まってくるかもしれません。

3.植物工場
私のコラムでも何回か触れてきましたが、植物工場では、環境がコントロールされた施設の中で葉物野菜などの植物を計画的に生産しています。自然光ではなくLEDなど人工光で生産を行っている植物工場では、天候に左右されず植物の成長をコントロールできるため、計画的に出荷をコントロールできます。必要な時に必要な分だけ出荷できるのが植物工場のメリットにもなりますので、植物工場は供給過多による食品廃棄を防止する1つの解決策になります。
また、植物工場では、環境をコントロールできるため、必要最低限の水、栄養で植物を生産することが可能になります。世界で利用される淡水の約70%は農業で利用されていると言われています。今後、人口の増加、地球温暖化などの影響により深刻な水不足になると、限られた水でより多くの食品を生産する必要が出てきますので、水不足の中、食品を確保する手段として、植物工場が選ばれる割合は増加していくと考えられます。今普通に食べている食品も10年後には、普通に食べられなくなっているかもしれません。
なるべくその様な事態を避けられるよう、個人的にもサステナブルな食品事情に関心を持って生活していきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
それではまた、次のコラムでお会いしましょう。
当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。
エバンジェリストによるコラムやIDグループからのお知らせなどを
メルマガでお届けしています。