
関連するソリューション

業務改革

AI
IDアメリカ
ハムザ・アフメッド
AIは本当に絶滅した恐竜をよみがえらせることができるのか?
結論から言えば、少なくとも現時点では「いいえ」です。とはいえ興味深いことに、AIはすでに、数万年前に絶滅した生物であるダイアウルフの復活に成功し、次はマンモスの復活に励んでいます。これは、いまのAIがチャットボットや画像生成にとどまらず、私たちが想像もしなかった分野で「できること」を書き換えつつあることを示す一例にすぎません。そして実は、これは去る8月12日から14日までラスベガスで開催された、AI分野で世界最大級かつ多様性に富むカンファレンスであるAI4で共有された、数多くの意外な物語のうちの一つに過ぎないのです。
摂氏43度の灼熱の太陽の下、ノーベル賞受賞の物理学者ジェフリー・ヒントンから各業界の経営者まで、数万人規模の人々が一堂に会しました。目的はただ一つ、AIの現在地だけでなく、その行き先、そして社会にもたらす意味を議論することです。
生成AIの台頭以降、雨後のたけのこのようにイベントが乱立する中で、AI4を際立たせているのはその出自です。ChatGPTやMidjourney、Stable Diffusionが一般に広がるずっと前に創設され、非AI企業が自社に人工知能をどう統合していくかを探るための「実務の場」としてスタートしました。そのDNAは今も色濃く残っており、誇大な期待よりも現場での活用に重心を置いており、金融やヘルスケアからエンタメ、インフラに至るまでに幅広い分野に渡っています。
本記事では、AI4の最も魅力的なハイライトをいくつかご紹介します。産業の形を根底から変え得る思いがけない応用例から、この技術が私たちの未来を岐路に立たせる中で直視すべき厳しい問いまで、要点を分かりやすくたどっていきます。

AIのゴッドファーザー
「AIは私たち人間よりはるかに賢くなるでしょう。」この身の毛もよだつ予測を口にしたのは、「AIのゴッドファーザー」と称されるジェフリー・ヒントン氏です。人工ニューラルネットワークの先駆的研究で現代のAI・機械学習の基盤を形づくってきたヒントン氏は、AI4の壇上で、汎用人工知能(AGI)の到来が私たちの想像よりはるかに近い可能性を強調しました。かつては30から50年先と見積もられていたものの、現在では5から20年のうちに実現しうると見ているのです。AIが人間の知性を超えるかどうかは、もはや「もし」ではなく「いつ」の問題であり、備えるべき時はまさに今と強調しました。
ヒントン氏が提案する安全策はAIに「母」を与えるという発想です。人間が支配・統制することを前提に設計されたシステムは、AIが人間を凌駕した時点で破綻するとヒントン氏は考えます。だからこそ、より深いレベル、すなわち「ケア」をAIに埋め込むべきだと主張しました。「これらのAIシステムに母性的な本能を組み込み、人を本気で大切にするようにしなければなりません」。権力欲ではなく、人間という「子ども」を守り導く責任感と保護の感覚を、揺るぎないコアとしてコードに刻み込むべきだというビジョンです。
AIは自らのコードを書き換え、改良できるために、単に私たちを出し抜く知性を持つだけでなく、人間の福祉と食い違う目標を発達させる危険性があります。そこで、共感とケアの枠組みを根幹に組み込むことが、競合相手ではなく守護者として進化させる道筋になりうる。これがヒントン氏の論点です。
もし機械が人間より賢くなる運命にあるのだとしたら、私たちに残された最善の希望は、支配を競うことではなく、むしろ彼らに育まれる存在になることなのかもしれません。大胆で、どこか詩的でもあるこの提案は、AI時代の設計思想に根本的な転換を迫っています。
AIのゴッドマザー
もしジェフリー・ヒントン氏が「AIのゴッドファーザー」だとするなら、「ゴッドマザー」もまた存在すると言えます。その称号にふさわしいのが、ヒントン氏の元門下生であり、現代AIの方向性に大きな影響を与えてきたフェイフェイ・リー氏です。コンピュータビジョン分野の先駆者として知られるリー氏は、2010年代のディープラーニングと画像認識の飛躍を後押しした巨大データセット「ImageNet(イメージネット)」を築き上げたことで最も広く認知されています。彼女の仕事がなければ、顔認識から自動運転に至るまで、今日のAI革命の多くは実現していなかったかもしれません。もっとも、ヒントン氏への深い敬意は変わらない一方で、リー氏の思想は彼とは分岐します。ヒントン氏が人類を守るためにAIへ「母性」を植え付けるべきだと警鐘を鳴らすのに対し、リー氏は別の道を主張しました。彼女にとってAIは、人間が支配する道具でも、依存すべき保護者でもなく、「パートナー」として扱うべき存在だと位置づけるのです。
リー氏の考える安全性は、人間の本能や愛情、ケアを機械に模倣させることからは生まれません。強固な監督体制、練り上げられた設計、そして人間中心の価値観に支えられるべきだと考えます。より賢い機械に出し抜かれたり脅かされたりしないための「生存競争」として課題を描くヒントン氏に対し、リー氏は協働のあり方を形づくることに焦点を当てます。重要なのは単に害を防ぐことではなく、AIが私たちの暮らしと仕事を積極的に良くしていくように設計することだ、という姿勢です。
リー氏にとって「信頼できるAI」を築く鍵は、機械に「思いやり」を教え込むことではなく、AIの土台に目的とガバナンスを組み込むことにあります。公平なアクセス、人間中心設計、倫理的なガードレール。こうした原則こそが、AIを恐れるべき知性でも寄りかかるべき保護者でもない、「真の協働者」へと導くのだと彼女は示しています。
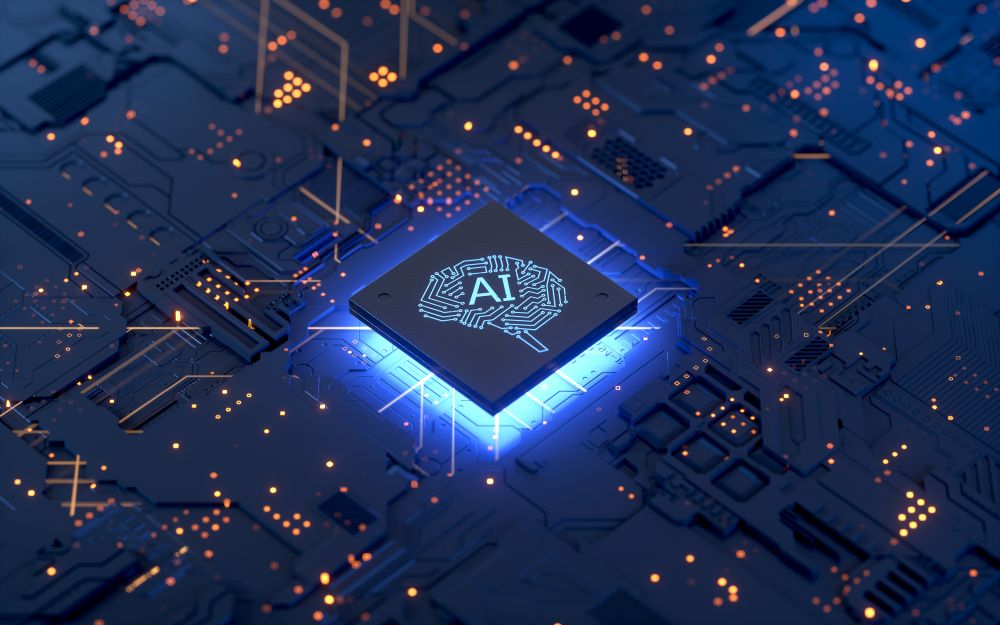
AIにセンティエンス(知覚力)は宿るのか
AIの「ゴッドファーザー」と「ゴッドマザー」が将来像で異なる見方を示す中、イベントで考えさせられた議題の一つが、この古くて新しい問いでした。AIはいつか「センティエンス(主観的な感覚・意識)」を持ちうるのか。これは研究室やカンファレンスの範囲を超え、SFや哲学、さらにはポップカルチャーにまで広がるテーマです。日本では、たとえばドラえもんは「考えるAIロボット」として想像されています。機械の意識への関心は何十年も続いてきましたが、その答えは今もなお複雑なままです。- 生成(エマージェント)説:生物の脳から意識が生まれたように、システムが十分な複雑性に達すれば自然発生的にセンティエンスが現れると考えます。
- 観念論(イデアリズム)的立場:純粋な物理主義を退け、「心」は物質構造を超えて存在すると見なします。AIはそれを本質的に体現できず、せいぜい近似にとどまるという見方です。
- 連続体(コンティニウム)説:意識はオン・オフのスイッチではなく連続的に存在し、初期的・部分的な「心のはたらき」が原始的な形で既存のAIにも芽生えているかもしれないと考えます。
- シミュレーション仮説:私たちが「心」と呼ぶもの自体が、脳という基盤上で走るシミュレーションだと捉えます。この論理に従えば、AIも同様のシミュレーションを行いうるが、それを真の意識と呼べるかは議論が割れます。
このように、問いは技術論というより哲学そのものです。別の登壇者は、AGIという概念自体も「動くゴールポスト」だと指摘しました。いまのAIを20年前の研究者に見せたなら、多分即座にAGIと呼んだかもしれません。ところが、ブレークスルーが起きるたびに私たちの期待値は上方修正され、かつて「知能」に見えたものは「単なる数学」に格下げされ、「本当の知能」のハードルはさらに遠のいていきます。
会場には確かな懐疑心も漂っていました。AIがまもなく、共感や推論、創造性まで人間らしく「振る舞える」ようになるかもしれません。しかし、それが意識の存在を意味するとは限りません。せいぜい見事な模倣であって、「生の体験」ではない可能性があります。それでも、もしAIがいつの日かわずかでも真の自覚に手をかけたなら、テクノロジーとの関係は根底から変わるでしょう。なぜなら、そのとき意識あるAIは、賢く振る舞うだけでなく、「私たちにとって本当に大切なこと」を理解できるかもしれないからです。
結局のところ、AIの知覚力をめぐる答えは、エンジニアだけが導けるものではありません。シリコンとコードの話であると同時に、「意識をどう定義するのか」という哲学の問題でもあるのです。
AIが「生活コーディネーター」になる日
TikTokが次に見たい動画を言い当て、Instagramが妙に「自分事」な投稿を流してくる。すでに私たちは、いわゆるAIの「生活コーディネーター」の初期形に触れているのです。AIの最大の強みはパターン認識であり、私たち自身が見落とすような行動やつながりをデータから見抜きます。しかもいまのAIはテキストだけでなく、音声・画像、さらには生体信号まで処理できるようになりつつあり、より個人に最適化された体験を組み立て始めています。企業もこの未来に大きく投資しています。大手小売は、AIを単なるレコメンド装置としてではなく、ユーザーの「意図から行動」までを導くパーソナライズされたな「旅路」を設計するための基盤と見なしています。カンファレンスで語られた例を挙げると、ネットでフィットネス情報をよく検索するのに実践が続かない人がいるとします。AIは「関心」と「動機」のギャップを検知し、自宅でできる短時間エクササイズをそっと促し、次にウェアや器具、ジム会員などを提案します。単に売るためではなく、「前進しているという感覚」をつくり、関与を高める設計なのです。
これは机上の空論ではありません。Amazon、Kroger、Dick’s Sporting Goodsのような企業は、AIによるパーソナライゼーションで購買体験の再設計を進めています。閲覧パターンから購買履歴までを解析し、在庫を最適化し、プロモーションを個別化し、顧客が言葉にする前のニーズを先回りする。狙いは、離脱を防ぎ、満足度を引き上げ、「買い物」と「ライフコーチング」の境界を曖昧にすることです。
もちろん、この流れには表裏があります。一方では、AIという「生活コーディネーター」は便利さや動機づけ、「わかってもらえている」感覚をもたらします。他方で、プライバシーや自律性、そして私たちの選択が本当に自分の意志なのか、それとも自分自身以上に自分を知るアルゴリズムに“そっと誘導”されているのか、という切実な問いを突きつけます。

AIと「デ・エクスティンクション(絶滅復活)」
ここまでお読みいただきありがとうございます。多くの方がいちばん気になっているテーマかもしれません。では、絶滅した動物はどうやって蘇らせるのでしょうか。これは米国のスタートアップ、Colossal Biosciences(共同創業者:ベン・ラム)が2021年から取り組んできた問いです。2024年には、同社がダイアウルフ(数万年前に絶滅)を「復活」させ、3頭の子どもを保護下に置いていると基調講演でプロセスを紹介しました。約2年にわたる試行の概要は次のとおりです。
プロセス
1.古代DNAの回収と読み取り保存状態の良い遺骸(骨や歯など)から古代DNAの断片をシーケンスします。断片化や損傷があるため、完全なゲノムがそのまま得られるわけではありません。同時に、行動・形態・特徴・生息環境などの情報を集め、動物像の全体像を把握します。
2.最も近縁の現生種を特定して比較
絶滅種の特徴(体格、頭骨・顎の形、被毛、代謝など)に関与したと思われる遺伝子をマッピングします。注記:ダイアウルフは「大きなハイイロオオカミ」ではなく、最近の灰色オオカミやコヨーテとの遺伝的交流がない高度に分岐した系統であることが2021年の画期的研究で示されており、「単純なクローン化」では片づけられない難しさがあります。
3.AIでゲノムの欠損を補完し、編集候補を優先づけ
機械学習を用いて損傷した配列を組み立て、欠落部分を推定(インピュテーション)し、どの変異が遺伝子調節やタンパク質機能、形質に影響するかを予測します。これはAlphaMissenseのような変異効果予測や、デ・エクスティンクション向けのAI主導バイオインフォマティクス基盤に類似するワークフローです。要するに、AIは「ゼロからゲノムを創る」魔法ではなく、再構築と設計判断を高速化します。
4.編集してクローン化
Colossalは、ハイイロオオカミのDNA編集を施し、イヌの卵子へ体細胞核移植を行い、代理母犬での妊娠・出産を経て3頭の子犬に至った、と説明します。同社はこれを「初の絶滅復活動物」と位置づけますが、批評家は「ディアウルフ的形質を一部持つ遺伝子編集ハイイロオオカミに過ぎず、種の復活とは言えない」と反論します。
AIが真価を発揮する場面
- 損傷した古代DNAからのゲノム組み立て・補完
- 形質再現に効く変異の選別(体格・被毛・頭骨など)
- 間違いの最小化や胚の生存性を最適化する設計探索
言い換えれば、AIはパイプラインを加速しリスクを減らす役割を担いますが、デ・エクスティンクションを「容易」にするわけではありません。
次の動物:マンモス
現在、チームはマンモスの復活に取り組んでおり、CEOが運用するX(旧Twitter)のページを通じて一般からの関心や提案も募っています。関心のある方は、ぜひアイデアを投稿してみてください。最後に
ジェフリー・ヒントン氏の提案する「AIの母」から、フェイフェイ・リー氏の掲げる「協働者としてのAI」、知覚力をめぐる哲学的議論、さらには大胆な絶滅復活の試みに至るまで、AI4が示したのは一つの明確な事実です。AIはもはや単なる道具ではなく、私たちが未来をどのように思い描くかを規定する決定的な力になりつつあります。イベントは、この時代の高揚と不安の両方を鮮やかに掬い上げ、進歩のビジョンとともに、私たちが直面する倫理的・社会的な分岐点をはっきりと浮かび上がらせました。本記事で触れられたのは、今年のAI4で語られた内容のごく一部にすぎません。日常を作り替えるAI、意識の境界、あるいは基盤技術そのものなど、特定のテーマをさらに深掘りしてほしい場合はお知らせください。AIの物語はまだ進行中で、次の章は私たちの想像以上の速さで近づいています。
当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。
エンジニアによるコラムやIDグループからのお知らせなどを
メルマガでお届けしています。




